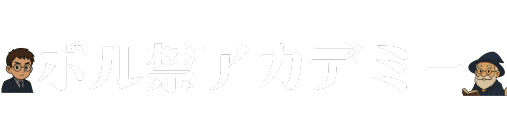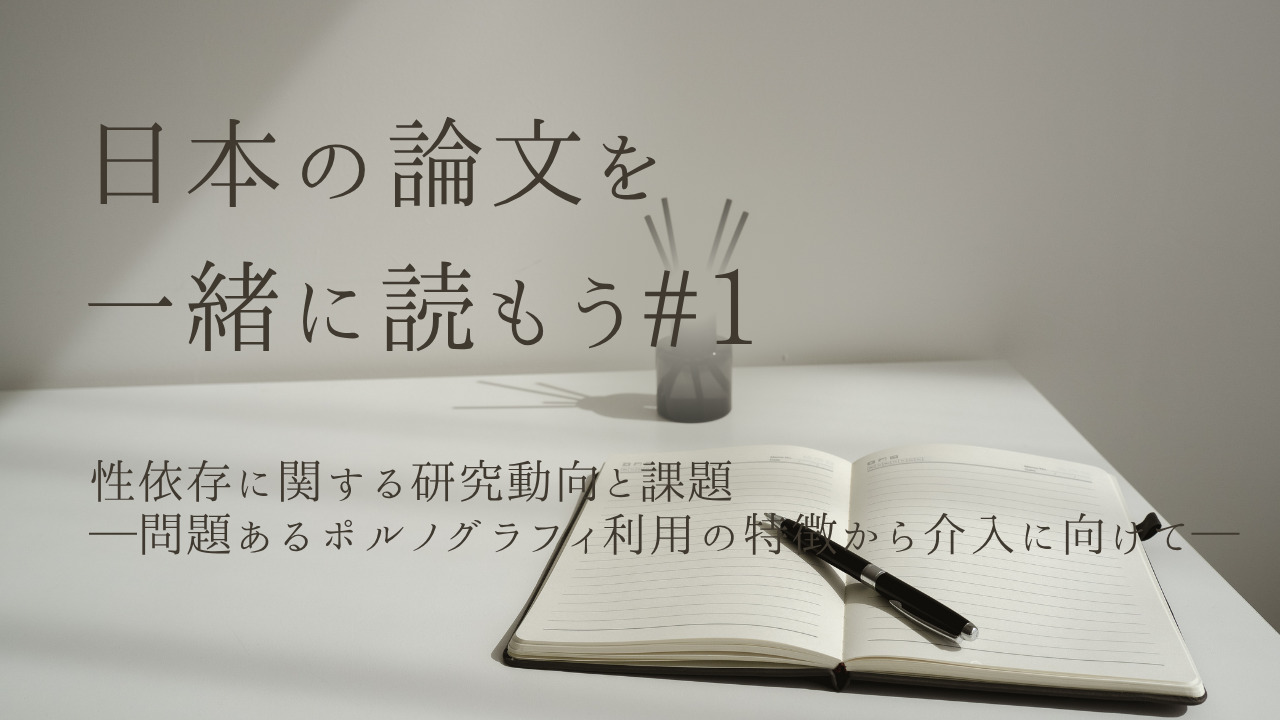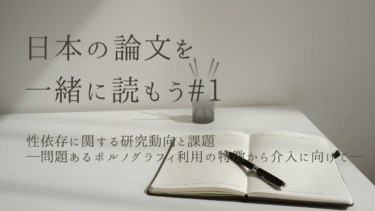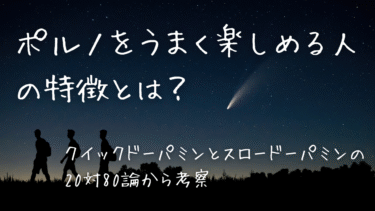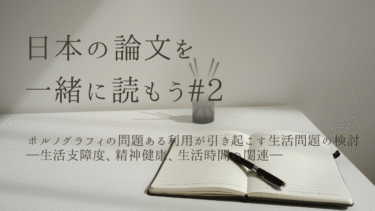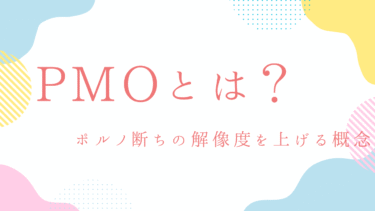「日本の論文を一緒に読もう」シリーズは、日本のポルノ依存症関連の研究論文を皆さんといっしょに読んでいくという企画です。
オープンアクセスの場合はそのURLも記載しますので、興味があればぜひ全文を読んでみてください。
それでは、すべてのポルノ依存症研究者に敬意を表して、丁寧に読んでいき、自分のポルノ断ちの改善につながるような知恵がないか確認してまいりましょう。
この論文について
さて、今回取り扱う論文のタイトルは、「性依存に関する研究動向と課題─問題あるポルノグラフィ利用の特徴から介入に向けて─」です。2021年に兵庫教育大学で発行されたものです。
現在、こちらの兵庫教育大学学術リポジトリから全文をダウンロードできます。
この論文は、「問題あるポルノグラフィ利用(Problematic Pornography Use:PPU)」に関する文献レビュー(既存研究の整理研究)です。
つまり、著者らが独自の調査を行ったものではなく、国内外の研究成果を幅広く読み解き、PPUに関する知見・課題・今後の方向性を整理したものです。
2021年時点で、諸外国と日本におけるポルノ研究がどこまで進んでいるのかについて理解できます。
海外の研究動向
近年、海外ではPPUをめぐる研究が急速に進展しています。インターネットの普及によりポルノへのアクセスが容易になった一方で、「利用をコントロールできない」「生活に支障をきたす」といった問題も報告されています。
これまでの主な発見は以下の通りです。
- PPUはICD-11(国際疾病分類)で「強迫的性行動症」と関連する概念とみなされている
- PPUは男性に多く、特に青年期に発症しやすい
- ポルノ刺激への反応性が高い人ほど、ポルノへの依存的傾向を示しやすい
- PPUは精神疾患(不安障害、ギャンブル障害、注意欠陥・多動性症など)と併存する
- 一方でポルノの娯楽的な利用は、日常生活に良い影響を与える可能性がある
また、欧米諸国では、PPUに苦しむ人が心理士や医師に相談し、治療や支援を受けるケースも増えているようです。
日本の現状と課題
一方、日本ではPPU研究はまだ発展途上です。
- 実証的な調査が少なく、発生率や特徴が十分に把握されていない
- PPUの診断や支援に関する専門体制が整っていない
- 性や依存に関する話題が社会的にタブー視されやすく、研究も支援も進みにくい
著者らは、こうした現状を踏まえ、「日本における実態の把握」と「文化的背景をふまえた介入研究」が今後の重要課題だと指摘しています。
この研究結果をポル禁にどう活用するか?
この論文自体は臨床的な介入研究ではありませんが、紹介されている知見の中にはポルキニスト(ポルノ断ちをしている人)にとって参考になる点があります。
たとえば、次のような情報は参考になりそうです。
- 心理療法のなかでも、認知行動療法やACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)、カップルセラピーがPPUに有効である可能性
- ACTにより、「ポルノ利用時間の減少と生活の質の改善」が示されていること
- とくにACTは、「否定的な感情や衝動を回避するためのポルノ利用」に効果的である可能性
本記事執筆者の私も、ACTは活用しています。こみあげてくる「ポルノをみたい」という渇望をありのままに見つめて、本当に自分に大切な行動を取ることができるようになります。とくにポルノ断ち初期にACTのアプローチを取り入れると効果的だと思います。
まとめ
この論文を通して見えてくるのは、2021年時点では、「PPUの定義も、治療法も、まだ確立していない」という現実です。
とはいえ、諸外国では研究は確実に進んでおり、
- 測定尺度(PPUSなど)の整備
- 心理療法の応用
- 社会的支援のあり方の検討
といった基盤が少しずつ整いつつあります。
日本でも、性依存やポルノ利用に悩む人が安心して支援を受けられる社会が一日でも早く実現することを願っています。
以上です。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
ポルノ断ち、無理せずがんばっていきましょうね!
ご意見などございましたら本記事下部の「お問い合わせ」より、お伝えいただけますと幸いです。